【早見表つき】手取りの計算方法とは?額面との違いもFPがわかりやすく解説
会社員は毎月の給与から所得税や住民税、社会保険料などが天引きされた「手取り」を受け取ります。 社会人...
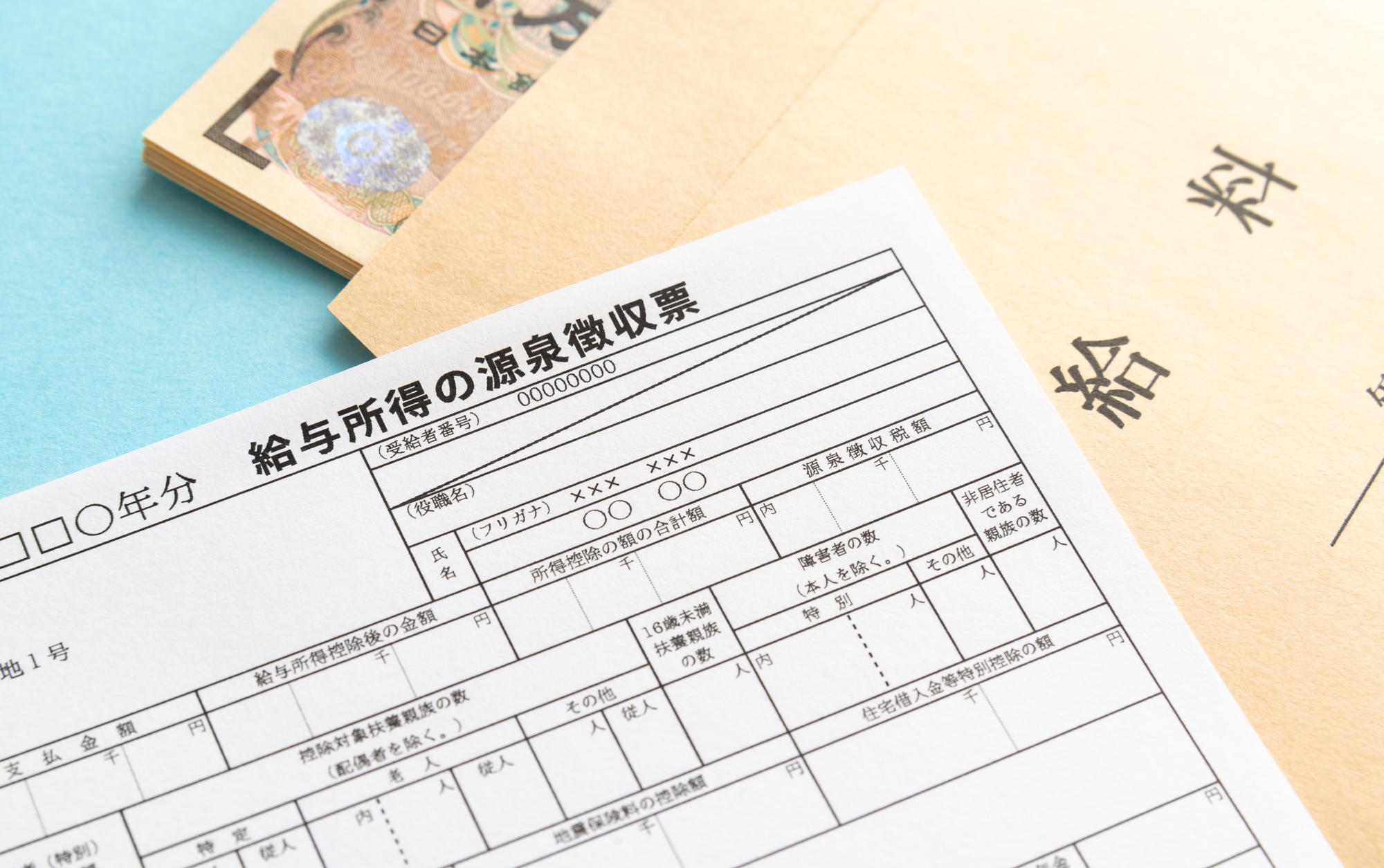 その他
その他会社員は毎月の給与から所得税や住民税、社会保険料などが天引きされた「手取り」を受け取ります。 社会人...
 資産運用
資産運用NISAは、2014年1月に開始した少額投資非課税制度の通称です。2024年からはこれまでのNISA...
 その他
その他勤めている会社に「ライフプラン手当(選択制企業型DC)」という制度があり、どのような制度か不思議に思...
 その他
その他物価や光熱費の高騰により、家計の負担は増え続けています。家計の支出状況を記録し節約につなげる手段とし...
 住宅ローン
住宅ローン日本銀行は2024年3月18日、19日の金融政策決定会合により、マイナス金利の解除を決定しました。三...
 その他
その他「30代の子育て世帯は、教育費や住宅ローンなどで支出が多く、貯金が思うようにできない」とお悩みではあ...
 資産運用
資産運用株式相場や為替相場を予測する方法の一つに「ファンダメンタルズ分析」という分析方法があります。 ファン...
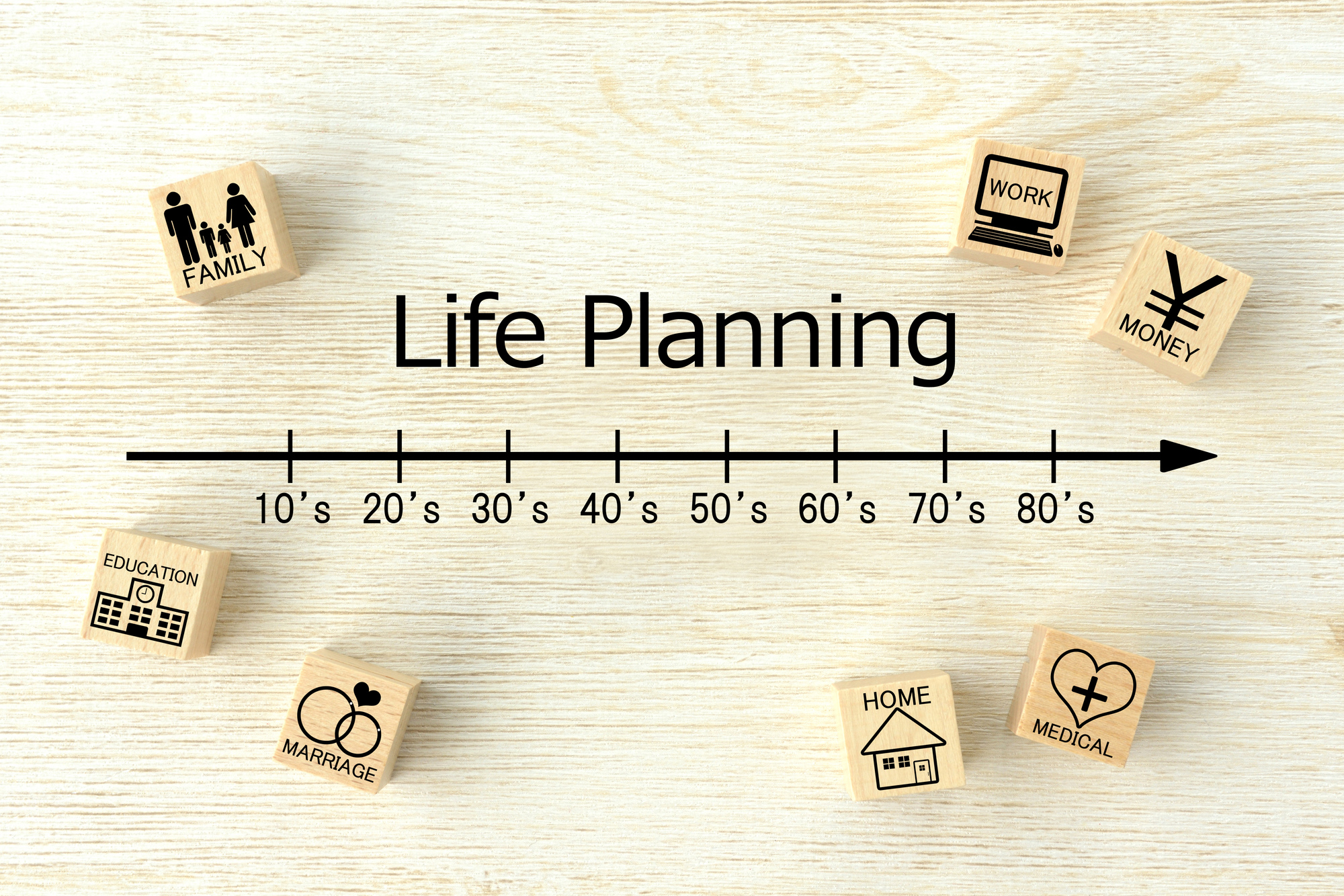 その他
その他「マイホームを購入したい」「老後をゆっくり過ごしたい」など、誰しも人生で叶えたい夢や目標を持っていま...
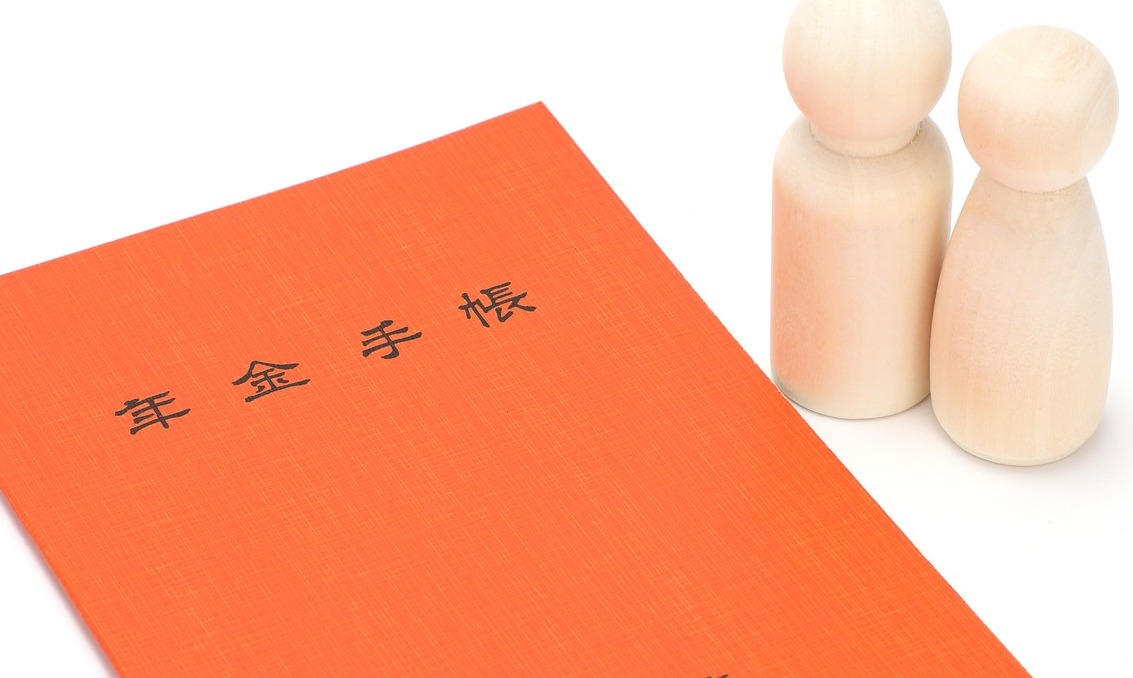 その他
その他年金は老後の生活のための制度というイメージがあるかもしれませんが、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と...
 その他
その他終活とは、残りの人生を有意義に過ごすためや、家族に負担をかけないために身のまわりの整理などをする活動...