介護費用の平均はいくら?自己負担を軽くする制度をFPが解説
 その他
その他
親の介護にかかる費用は、平均で約540万円(2人以上世帯・2024年度調査)にのぼると試算されています。公的な介護保険制度を利用したとしても、家計にとっては大きな負担になり得ます。特に初期費用として、リフォーム代や介護用品の購入費がかかるケースも少なくありません。
本記事では、介護費用の平均額や制度による負担軽減の方法、準備のポイントをFPがわかりやすく解説します。
特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
マネプロに相談しよう
目次
親の介護にかかる平均費用とは
親の介護に必要なお金は平均約540万円です。実際に親や親戚が歩けなくなったり認知症になったりすれば、子の世代が介護費用を出すこともあります。
ここでは生命保険文化センターの調査結果より、介護にかかる平均費用について解説します。
介護費用は平均約540万円
生命保険文化センターが公表している「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」によれば、平均して約540万円の介護費用がかかります。
2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査〈2人以上世帯〉
同資料によれば、介護に一時的にかかった費用の平均は47万円、月々の介護費用の平均は月9万円、平均的な介護期間が55.0か月(4年7か月)です。
単純な計算ですが、「47万円+9万円×55.0か月=542万円」と、500万円以上の費用がかかる計算です。
介護が必要な方の状況はそれぞれ異なりますが、ひとたび介護が必要になるとこれだけのお金がかかってくる場合があるということを押さえておきましょう。
月額介護費は平均9万円
毎月の介護費用は平均9万円。在宅5.2万/施設13.8万円と大きな差があります。介護に必要な費用の平均は9万円というデータになっており、これが毎月のようにかかるとかなりの負担になることが分かります。
ただし、介護を行った場所ごとに介護費用が大きく異なる点に注意が必要です。在宅介護では毎月の支出が5.2万円と平均よりかなり低い一方、施設での介護の場合は平均で毎月13.8万円の費用が発生することがデータで示されています。
また、要介護度が上がるほど月額負担は増加します。例:要支援1=5.8万円/要介護5=11.3万円。
<要介護度と介護費用の平均>
| 要介護度 | 毎月の介護費用の平均 |
| 要支援1 | 5.8万円 |
| 要支援2 | 7.0万円 |
| 要介護1 | 5.4万円 |
| 要介護2 | 7.5万円 |
| 要介護3 | 8.5万円 |
| 要介護4 | 12.4万円 |
| 要介護5 | 1.3万円 |
介護期間は平均4年7か月
介護が必要な期間は平均で約4年7か月(55.0か月)(4年以上:42.7%)。4年以上続くケースが4割を超えるため、長期化を前提に備えることが重要です。
<介護の期間と割合>
| 介護の期間 | 割合 |
| 6ヵ月未満 | 6.1% |
| 6ヵ月~1年未満 | 6.9% |
| 1~2年未満 | 15.0% |
| 2~3年未満 | 16.5% |
| 3~4年未満 | 11.6% |
| 4~10年未満 | 27.9% |
| 10年以上 | 14.8% |
| 不明 | 1.3% |
介護保険制度で費用負担を軽減
前章で紹介した金額は、公的な介護保険サービスを利用することが前提の金額です。介護保険を利用したとしても1人の介護で平均約540万円の費用がかかることも考えると、介護が必要になった際はすぐに要介護認定の手続きをすることが大切です。
介護費用の準備には、公的な『介護保険制度』の仕組みを知っておくことが欠かせません。市区町村に要介護認定を申請すると、要介護または要支援の区分が決定され、それに応じた支給限度額が設定されます。この限度額内であれば、介護サービスを原則1〜3割の自己負担で受けることができます。
要介護・要支援ごとの1ヵ月あたりの利用限度額と利用者負担額(自己負担割合が1割の場合)は以下のとおりです。
<介護保険サービスの要介護度別利用限度額・自己負担額一覧>
| 要介護度 | 1ヵ月あたりの利用限度額 | 利用者負担額(1割負担の場合) |
| 要支援1 | 56,000円程度 | 5,600円程度 |
| 要支援2 | 117,200円程度 | 11,720円程度 |
| 要介護1 | 186,500円程度 | 18,650円程度 |
| 要介護2 | 219,200円程度 | 21,920円程度 |
| 要介護3 | 300,800円程度 | 30,080円程度 |
| 要介護4 | 344,100円程度 | 34,410円程度 |
| 要介護5 | 402,800円程度 | 40,280円程度 |
介護保険で自己負担が3割に
介護保険では、介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。自己負担割合は介護サービスを受ける本人や、同一世帯の65歳以上の配偶者や親族の合計所得で決まります。
厚生労働省によれば、自己負担割合の決まり方は以下のとおりです。
※第2号被保険者、資料損民税非課税者、生活保護受給者の場合、上記のフローにかかわらず、1割負担。
出典:厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会(第107回) 給付と負担について(参考資料)」
本人の合計所得が160万円未満なら1割負担です。また、合計所得が160万円以上、220万円以下ということなら、年金収入とその他合計所得が280万円未満(夫婦世帯は346万円未満)なら自己負担1割で介護サービスを利用できます。
ご自身の両親が要介護になりそうな時から、年金やその他の所得を計算し、自己負担が1~3割のどこに当てはまるかシミュレーションしてみましょう。
毎月の介護サービスの自己負担額が大まかに分かるため、介護生活をイメージしやすくなります。
介護保険の支給限度額に注意
介護保険は自己負担割合1~3割で利用できるのは前章で解説したとおりです。
介護保険サービスは、要介護度に応じて利用できる上限額が決まっています。その上限内であれば、自己負担は1〜3割程度に抑えられますが、超えた分は全額自己負担となるため注意が必要です。
いくつかの介護サービスを同時に利用すると、介護費用が高額になってしまう可能性があります。
介護施設と在宅介護の費用比較
実際に親や親戚を介護する場合、「自宅で介護をする」「施設で介護をする」という選択肢があります。すでに解説したとおり、基本的に施設で介護したほうが、かかる費用は高額になります。
ここでは、自宅での介護と施設での介護でかかるお金の費用感について紹介します。
在宅介護にかかる費用とは
在宅での介護を選択した場合、まず検討が必要になるのは自宅のリフォーム費用です。生命保険文化センターによればリフォームを含む一時的な費用に平均で74万円がかかっています。
参照:生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」
その代わり、施設と違って施設の利用料は発生しません。ポータブルトイレやシャワーチェアなどのレンタル費用やおむつ代、食事代などはリフォームとは別に必要になるでしょう。
例えば自己負担1割の要介護2の人の場合、自己負担限度額は21,920円程度です。ただし、限度額を超過した際、その超過分が、民間の介護サービスを利用した場合は全額が自己負担になるので注意が必要です。
施設介護の費用と注意点
施設に入所した場合、生命保険文化センターの資料からも分かる通り、介護費用が高額になる傾向にあります。
ただし、公的な介護施設と民間の介護施設のどちらを選ぶかによっても費用感は変わります。
施設ごとに公的・民間どちらに分類されるか、以下にまとめたので参考にしてみてください。
<公的・民間介護施設の分類>
| 公的な介護施設の例 | 民間の介護施設の例 |
|
・特別養護老人ホーム |
・介護付き有料老人ホーム |
介護施設でも介護サービス分は介護保険が適用されますが、保険適用外の費用として「居住費」「食費」「管理費」などが発生します。また個室にするか大部屋にするかによっても費用は大きく異なるでしょう。
一例として、都内にある介護付き有料老人ホームに要介護3の人が入居する場合の費用の例を紹介します。
<都内の介護付き有料老人ホーム(要介護3)の月額費用例>
| 家賃 | 90,000円 |
| 管理費 | 54,500円 |
| 食費 | 56,040円 |
| 介護保険サービスの自己負担 | 21,676円 |
| 合計 | 222,216円 |
高額介護の負担を軽くする制度
ここまで紹介したとおり、介護費用が1~3割負担でも施設に入居したり一定以上の介護サービスを利用したりすれば、自己負担が高額になりやすいです。
ただ、公的制度には一定以上の自己負担が戻ってくるような制度もあります。介護の準備をする人は、今から紹介するような制度の概要を知っておきましょう。
高額介護サービス費
介護保険のサービス費用は所得区分によって月の上限が設定されます。
高額介護サービス費支給制度とは、ひと月あたりの介護サービス利用に対する自己負担が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。対象は保険が適用される介護サービスに限られ、リフォーム費や施設の居住費・食費などは含まれません。
高額介護サービス費の負担限度額(月額)は以下のとおりです。
<高額介護サービス費の負担限度額(月額)>
| 区分 | 負担の上限額(月額) | |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
| 市町村民税非課税世帯 | 年全の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している | 15,000円(世帯) | |
出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費は、所得が低い人の介護施設における食費・居住費を軽くする制度です。
施設に入居したときの食費や居住費は基本的に自己負担ですが、所得の低い人に対しては自己負担限度額を超えた分が介護保険から支給されるようになります。
ただし、自動的に適用されるわけではない点に注意が必要です。特定入所者介護サービス費を受け取りたいなら住まいの市町村への申請が必要です。
仕事と介護を両立する制度とは
会社員の人は、仕事と介護の両立をするのが非常に大変です。そこで、これから紹介する公的制度を上手に利用しましょう。
介護休業制度
介護休業制度は、労働者が要介護状態にある家族を介護する場合に適用される休業制度です。
対象家族1人につき通算93日までの範囲内で、3回まで介護休業を取得できます。対象家族は父母や子供だけでなく、配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹も含みます。
ただし、パートやアルバイトなど有期雇用の場合は以下の条件を満たすことが必要です。
| 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと 出典:厚生労働省「介護休業とは」 |
また、企業によっては短時間勤務やフレックスタイム制など柔軟な働き方を認める場合もあります。これらの制度と介護休暇を組み合わせることで、より現実的に仕事と介護を両立させやすくなるでしょう。
医療費負担を軽くする制度まとめ
介護費用と合わせて介護する側が心配するのは、医療費に関することではないでしょうか。要介護の人は毎週のように病院に通うことも珍しくなく、場合によっては医療費が高額になります。
その時になって慌てなくても良いように、医療費を軽くする公的制度も今のうちに把握しておきましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヵ月(同じ月の1日~末日)のうちに医療機関に支払う医療費や薬局で支払う薬代などが一定額を上回った場合、その差額が払い戻される制度です。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満か70歳以上か)や、それぞれの所得によって異なります。
例えば70歳未満で月収が27~51.5万円未満の人の自己負担限度額は以下のように計算できます。
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
また、同一世帯で直近12ヵ月に3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目以降の自己負担が軽減される「多数該当」という制度もあります。
高額介護合算療養費制度
高額療養費制度とは、同一世帯において、1年間に支払った「医療保険」「介護保険」の自己負担合算額が一定以上の高額になった場合に、限度額を超えた分が払い戻される制度です。
医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額は以下のとおりです。
<70歳以上の人がいる世帯の自己負担額例>
| 負担区分 | 自己負担限度額 |
| 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 |
| 課税所得145万円未満 | 56万円 |
| 市町村民税非課税 | 31万円 |
| 市町村民税非課税(所得が一定以下 | 19万円 |
なお、年間で支払った医療費が一定額を超える場合は『医療費控除』の対象にもなります。確定申告が必要ですが、所得税の軽減につながるため該当する場合は活用を検討しましょう。
介護費用に備えるための早期準備のポイント
最後に、高額な介護費用をまかなうための対策や、介護負担を減らしたりする対策について紹介します。
いきなり介護が始まると、働き盛りの世代は急な介護に対応できないことがあります。いつ介護が始まっても良いように、介護する側が若く時間があるうちから準備を進めておきましょう。
役割分担や介護の方針を事前に決めておくことが重要
介護に関して気になることはお金だけではありません。介護の方針や役割分担を決めておくことも重要です。
まず、介護を受ける人の希望を聞いたうえで、「どんな介護をしていくのか」ということを介護する側で話し合いましょう。介護をする人の時間やお金の余裕は家庭ごとに異なるため、必ずしも介護される側の希望を実現できるか分からないためです。
在宅で介護するなら毎月の自己負担を抑えられますが、誰かが同居したり近くに住んだりしてサポートしなければいけません。それができないなら施設への入居を検討することになりますが、費用をどう工面するかという問題が生じます。
また、介護する人に兄弟姉妹がいるなら、1人が全てを負担しないような役割分担を決めておくことも大切です。役割分担を決めておくことで急な状況変化でも対応しやすくなり、家族の関係性悪化を防ぐこともできます。
NISAやiDeCoで介護に備える
親が介護用の貯金を用意していない場合、子供の世代で介護費用を出し合うことになる可能性もあります。いつでも引き出せる貯金で貯めておくのがセオリーですが、低金利の現在では普通預金だけではなかなか資産は増えません。資産の一部を投資に回し、効率的に資産運用する方法も検討しましょう。
特におすすめできるのは「NISA」「iDeCo」といった非課税制度を利用することです。
NISAは最大1,800万円まで投資でき、その枠のなかで得た利益が全額・無期限で非課税になります。金融庁が認めた特定の投資信託を毎月コツコツ積み立てられる「つみたて投資枠」もあり、初心者でも資産形成がしやすいです。
必要なときに引き出すこともできるため、比較的早い段階で介護が始まったときに介護費用として利用できます。
iDeCoは「個人型確定拠出年金」の略称で、自分で運用商品を選んで運用する私的年金制度です。
拠出した金額には職業によって上限が決まっていますが、拠出額の全額が所得控除になって所得税や住民税が安くなる税制メリットを得られます。運用期間中の利益は非課税で受け取る際にも控除が受けられる点も魅力です。
60歳以降にならないと受け取れないデメリットがありますが、60歳以降に両親の介護が発生した場合や、自分の老後資金をメインに資産形成したい場合に有効です。
民間介護保険の特徴と活用法
公的介護保険では自己負担割合の範囲内で一定のサービスを受けることはできますが、民間サービスや施設の居住費などは介護保険の対象外です。
そんなときのために、民間の介護保険を利用するという選択肢もあります。民間の介護保険では一定の要介護状態になったり、保険会社が指定する一定の基準を満たしたりした場合に、給付金を受け取ることができます。
公的介護保険のように介護という現物給付ではなく、金銭を受け取れるのが大きな特徴です。給付金の使途に制限がないため、介護保険対象外のサービスの支払いなどに柔軟に利用できます。
まとめ
介護にかかる費用は状況によって異なりますが、500万円以上必要になることもあります。公的な制度を理解して活用すること、そして早めに準備を始めることが重要です。
不安がある方は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談し、自分に合った備え方を見つけていきましょう。
マネプロに相談しよう
特定の金融機関に偏らない立場で、幅広い選択肢からお客様に最適なものをご案内する“おかねのプロ“です
- ID:BM–730


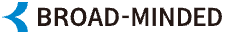


.png)


