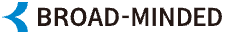会社員が知っておきたい福利厚生・資産運用制度とは?初心者向けにFPが解説
 その他
その他
年金不安や物価の上昇などさまざまなリスクがある現在、今ある仕組みを上手に活用することが、資産を守りながら増やすポイントになっています。資産運用といえば預貯金やNISAのように個人で投資をする仕組みもありますが、実は会社の福利厚生を活用して資産形成をする方法もあります。
しかし、会社にはさまざまな福利厚生がある一方で、入社時以外はあまり詳しい説明がなく、せっかく利用できる制度があるのに、知らないまま活用できていないという方も多いかもしれません。
本記事では資産運用の基本をおさらいしつつ、会社の福利厚生のなかでも資産運用に役立つおすすめの制度を紹介、解説します。
そもそも「資産運用」とは何か
資産運用とは、預貯金(普通預金・定期預金など)、株式、債券、投資信託などの金融商品を利用し、手持ちの資産を増やすことを指します。
かつて高度経済成長期の日本は「銀行に預けていればお金が増える」と言われているほど、金利が高く、リスクをとって資産運用をしなくても一般的な生活を送ることができていました。
しかし、バブルが崩壊したあとにマイナス成長となった日本で日本銀行は「ゼロ金利政策」を実行し、普通預金や定期預金に預けているだけではお金がほとんど増えない世の中になりました。
さらに、少子高齢化が深刻化しており、公的年金だけでは老後資金が不安視される時代になりました。
このような背景から、今のうちからできる資産運用を考えることが大切になっています。
資産運用はNISAやiDeCoなど個人で進める方法もありますが、会社によっては、資産運用に活用できる福利厚生の仕組みを備えている場合もあります。
福利厚生の仕組みを資産運用に活用できる
福利厚生の中には、資産運用に活用できる仕組みがあります。
会社の福利厚生には、企業型確定拠出年金や持株など、資産運用に活用できる仕組みがいくつかあります。
これらの制度を利用することで、給与天引きや税制優遇などのメリットを受けながら、無理なく資産形成を進めることができます。
実際に、福利厚生の資産運用制度を利用している人は増えています。
【企業型確定拠出年金の加入者数】
| 加入者数 | |
| 2019年3月末 | 691万人 |
| 2024年3月末 | 830万人 |
【持株会の加入者数】
| 加入者数 | |
| 2016年 | 272万人 |
| 2021年 | 298万人 |
企業型確定拠出年金や持株会など、株式や投資信託を運用できる仕組みはいずれも最新データと5年前を比べると加入者数が増加しており、注目度が高いことがわかります。
物価高や将来的な増税、年金不安などさまざまなリスクがあるなかで安心して老後生活を迎えるためにも、現役世代のうちから今ある制度を活かしながら、将来に備えていくことが重要です。
会社員をしながら投資家に!資産運用の初心者でも資産形成ができる福利厚生
会社の福利厚生に資産運用の仕組みがあれば、特別な知識がなくても、会社員として働きながら効率的に資産形成を進めることができます。
会社によって福利厚生は異なりますが、以下のような制度があれば資産運用に利用できます。
- ・一般財形貯蓄
- ・財形住宅貯蓄
- ・財形年金貯蓄
- ・企業型確定拠出年金
- ・持株会
- ・ストックオプション
ここからは、資産運用の初心者でも取り組みやすいそれぞれの制度の特徴やメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
おすすめ制度①一般財形貯蓄とは
財形貯蓄とは、給与や賞与から天引きすることで自動的に積み立てることができる貯蓄のことで、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つがあります。
一般財形貯蓄は貯蓄を始める年齢に制限がなく、資金使途が自由な貯蓄制度です。預け始めてから1年間は払い出し不能ですが、それ以降はいつでも引き出せるため他の2つの財形貯蓄よりも流動性が高い特徴があります。
また、複数の金融機関との契約も可能で、原則として積立限度額もありません。
一般財形貯蓄のメリット
一般財形貯蓄は積立の利用目的が問われることがなく、用途を定めることなく自由に積立が可能という点がメリットです。結婚式やハネムーン、教育資金や車の購入費用など、さまざまな用途に自由に利用することができます。
また、引き出しも基本的に自由で、預入れより1年経過後であれば全額または一部引出しをしても契約が無効になることはありません。
一般財形貯蓄のデメリット・注意点
一般財形貯蓄のデメリットは、他の制度と違って非課税制度がないことです。
財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄のような非課税の優遇がないため、給与天引きが行われる以外のメリットはあまり大きくありません。
また、一般財形貯蓄の金利は金融機関ごとに異なります。勤務先が契約している金融機関に限りますが、選択できる場合は、どの金融機関の金利が高いか比較検討し、もっとも金利が高い金融機関を選択することがおすすめです。
おすすめ制度②財形住宅貯蓄とは
財形住宅貯蓄も、一般財形と同じく「財形貯蓄」の一種です。一般財形との違いとして、使用用途が住宅の購入・建築・リフォームなどに限定されていることが挙げられます。また、原則として1人1契約のみ、契約の年齢が55歳未満であることや、積立期間が原則5年以上であるといった制約もあります。
他の財形貯蓄との併用は可能ですが、複数の金融機関との契約はできません。
財形住宅貯蓄のメリット
財形住宅貯蓄を活用すると、まず給与からの天引きによって自動的に住宅資金を貯められるというメリットがあります。
そのほかに、一般財形貯蓄にはない大きなメリットに、非課税措置の存在があります。財形住宅貯蓄は、元本550万円とその利息について非課税になります。財形年金貯蓄も利用している場合、2つの制度を合わせて元利合計550万円までの利子等が非課税です。
また、目的外での払い出しも可能です。後述する企業型確定拠出年金は原則60歳までは投資した元本や利益を引き出すことができません。それと比較して、途中での払い出しができることは大きなメリットといえるでしょう。
さらに、財形住宅貯蓄を利用していると、「財形持家融資制度」を利用できます。財形住宅貯蓄を利用する労働者に対して、貯蓄残高に応じて住宅を建設、購入またはリフォームするための資金を事業主、事業主団体及び福利厚生会社を通じて融資してくれる制度です。
財形住宅貯蓄のデメリット・注意点
財形住宅貯蓄のデメリットとして、まず挙がるのが元本割れのリスクです。財形住宅貯蓄の運用先が保険会社や証券会社の場合、保険や投資信託などの金融商品の返戻率や商品価格が変動するため、市場の動向次第では受け取れる金額が積み立てた金額を下回ることがあります。
ただし、財形住宅貯蓄の運用先が預貯金の場合には元本割れのリスクなく運用できます。財形住宅貯蓄の運用は勤務先が契約している金融機関で行われるため、財形住宅貯蓄を始める際は契約している金融機関の投資先を確認して、リスクがある場合には慎重に検討しましょう。
また、目的外の払い出しができるメリットはあるものの、財形住宅貯蓄を目的外で払い出した場合は積立金に20.315%が課税されます。過去5年間分の利子も課税対象となるため、払い出しをするかは慎重に検討しましょう。
おすすめ制度③財形年金貯蓄とは
財形年金貯蓄は文字通り、老後資金を作るために活用できる財形貯蓄です。財形住宅貯蓄と同様に55歳未満の方が契約できて契約期間は5年以上、60歳以降には5年以上20年以内の期間で年金として受け取ることができます。
財形住宅貯蓄と同様に利子などに対する非課税優遇があり、財形住宅貯蓄と合わせて「元利合計550万円」までに生じた利息などが対象です。
公的年金だけでは将来の老後生活に不安を感じる方は、年金収入をカバーする目的で始めるのがおすすめです。
財形年金貯蓄のメリット
財形年金貯蓄のメリットは、財形住宅貯蓄のメリットと大きくは変わりません。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて元本550万円までの利息が非課税であり、本来なら引かれる20.315%の税金を節税して多くの金額を手元に残すことができます。
また、会社によっては、財形貯蓄制度に加入している労働者に奨励金という名の給付金を支払ってくれることもあります。
財形年金貯蓄のデメリット・注意点
財形年金貯蓄は金利が低めに設定されていることが多く、資産を大きく増やすのには向いていません。同じく年金に関する制度である確定拠出年金で投資信託に投資するときのほうがリスクがある分、長期的には財形年金貯蓄よりもはるかに大きな金額まで資産形成ができる可能性があります。
また、受け取り可能年齢に制限がある点もデメリットです。財形年金貯蓄の受け取り開始年齢は満60歳以上で、5年以上の期間にわたって受け取るという条件があります。早期退職しても受け取れるのは60歳からであり、受け取りタイミングを加味して老後資金の準備をしておく必要があります。
また、財形年金貯蓄は、財形貯蓄制度を取り入れている企業でのみ利用できます。転職先に財形貯蓄制度がないと積立を続けられないため、財形貯蓄を始めるなら今の会社に長く働くことが必要になるかもしれません。
おすすめ制度④企業型確定拠出年金とは
企業型確定拠出年金は「企業型DC」とも呼ばれており、会社員が利用できる退職金制度です。企業型確定拠出年金は企業が掛金を拠出し、運用は従業員自身が行います。会社の掛金に従業員も掛金を追加で拠出できる「マッチング拠出」を利用できるケースもあります。
積み立てた年金原資は将来的に年金もしくは一時金で受け取れます。ただし、原則60歳になるまでは引き出すことはできません。
運用商品は定期預金、保険、投資信託の3種類があり、投資信託を選択することで元本保証がされない代わり、将来的に受け取る金額を大幅に増やすことも可能です。
企業型確定拠出年金のメリット
企業型確定拠出年金は将来の老後資金を効率的に増やすための制度としておすすめで、主に以下の3つのメリットがあります。
- ・掛金や運用益が非課税
- ・各控除で税制メリットを得られる
- ・個人型との併用も可能
企業型確定拠出年金の掛金のうち、事業主掛金は個人の所得と見なされないため、所得税等が非課税になる特性があります。加入者が事業主に上乗せで掛金を出し合う「マッチング拠出」の分も全額所得控除になります。
また、運用中に得た配当金や売買益などの利益の全額が非課税です。通常なら配当金や売買益を得ると20.315%の税金がかかりますが、企業型確定拠出年金では税金として納めるはずの金額まで再投資に回すことができます。
企業型確定拠出年金は、iDeCo(個人型確定拠出年金)と併用が可能という点もメリットです。事業主と自身の掛金合計額が月額5万5,000円を超えることができない金額までと制限はありますが、毎月の上限まで投資がしやすくなり、より効率的に運用できるようになります。
ただし、すでに「マッチング拠出」を利用している場合は、企業型確定拠出年金とiDeCoの併用ができません。
企業型確定拠出年金のデメリット・注意点
事業主掛金と運用益の両方が非課税という大きなメリットのある企業型確定拠出年金ですが、以下のようなデメリットがあることも知っておきましょう。
- ・将来の年金額が確定しない
- ・60歳になるまでは引き出せない
企業型確定拠出年金は、掛金の運用結果に基づいた金額を受け取れるため、将来の年金額は資産運用の開始時に確定しません。運用の結果次第では受け取れる老後資金が想定よりも少なくなる可能性もあります。
また、企業型確定拠出年金は原則として60歳になるまで引き出すことができません。受け取り開始可能年齢は、加入者期間ごとに以下のように定められています。
【企業型確定拠出年金の加入期間と受け取り開始年齢】
| 必要な通算加入者等期間 | 受け取り開始可能年齢 |
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
子どもの教育費用や住宅ローンの頭金、入院費用等、急に高額の支払いが必要な場面でも確定拠出年金に拠出したお金を頼ることはできません。
おすすめ制度⑤持株会とは
持株会は、自社の株式を毎月一定金額ずつ購入していく福利厚生のことです。会社によっては時価よりも安く株式を購入でき、業績が向上して株価が値上がりすれば大きな利益を得ることもできます。
ただ、持株会以外に自分でも投資してしまうと、会社の経営状況がよろしくないと含み損になる可能性もあります。自分で投資するときは持株会で投資している自社株とは異なる銘柄に投資するなど、リスクヘッジを事前にしておくことが大切になります。
持株会のメリット
株式は通常100株単位での売買になり、株価が1,000円でも10万円以上の自己資金が必要です。いっぽう、持株会は、1株単位で株式を購入できます。毎月数千円から投資を開始できるため、日常生活に影響しない範囲で投資することが可能です。
また、企業によっては自社株の購入の際に「奨励金」を受け取ることができ、自分だけで投資するよりも効率的に資産形成を進められます。
奨励金の金額や割合は企業ごとに異なりますが、例えば「投資額の10%を奨励金として受け取れる」という企業なら5,000円の投資で5,500円分の株式を購入できます。
持株会のデメリット・注意点
株式投資は通常、市場で取引が行われているタイミングならいつでも自由に売買できます。一方の持株会は任意のタイミングでの売却はできません。また、単元株(100株)未満の株式を売却するには持株会を解約して買い取ってもらうなどの手続きが必要です。
購入した自社株式の株価が大きく上昇してすぐに売りたいときにも瞬時に売買ができず、思ったようなキャピタルゲインが得られないという可能性があることは覚えておきましょう。
また、持株会だけで資産運用すると会社の業績への依存度が高まる点にも注意しないといけません。会社の業績が悪化すると株価の下落と給与・賞与の減額が重なり、保有資産が一気に目減りする可能性もあります。持株会に加入している方でも、リスク分散の意味で他の銘柄への投資や預貯金を進めましょう。
また、あくまで個人ではなく持株会の名義で取引することから、自社の株式が「単元株の保有で株主優待がある」というタイプでも株主優待はもらえません。株主優待を得るなら、持株会以外に自分で投資が必要です。
おすすめ制度⑥ストックオプション
ストックオプションは、自社に勤務する役員や従業員が、事前に定めた価格で一定期間内に一定数の自社株式を購入する権利のことです。役員や従業員は株価が高くなったタイミングでストックオプションの権利を行使することができ、株価上昇分の利益を得ることができます。
ストックオプションと持株会は似たような仕組みに感じるかもしれませんが、自社株の取得権利の対象者が異なります。ストックオプションは権利を付与された人だけが自社株を取得できますが、持株会では自社内の人なら誰でも申請することで自社株式を取得できます。また、従業員に該当しない役員や外部の利害関係者なども権利付与の対象です。
なお、自社に投資することで利用券を得られる「有償ストックオプション」、企業が役員や従業員に無償で権利を付与する「無償ストックオプション」などの種類に分かれます。
ストックオプションのメリット
ストックオプションは、権利行使価額よりも株価が上回っている場合に利益を得られる仕組みです。株価を上昇させるには業績をアップさせる必要があり、ストックオプションの利益を得る名目で仕事へのモチベーションが上がることが期待できます。
また、自分自身で投資する通常の株式とは異なり、ストックオプションには損失リスクがありません。権利行使価格よりも株価が下落しても権利を行使さえしなければ損失は発生しないため、冷静に売り時を判断できるでしょう。
株式投資と違って先に投資して株式を保有しておく必要もないため、初期費用なしで資産運用を始められます。
ストックオプションのデメリット・注意点
ストックオプションのデメリットは通常の株式投資と同様、株価が下落し権利行使価額を下回ると利益を得られない点です。株価が下落するとせっかくストックオプションを持っていても利益を得ることができず、仕事に対してのモチベーションにも影響するかもしれません。
また、ストックオプションの権利を行使して売却益を得たあとは、仕事に対するモチベーションを維持しにくいという点もデメリットとして考えられます。
まとめ
福利厚生を活用した資産運用には財形貯蓄、企業型確定拠出年金、持株会、ストックオプションなど、さまざまな種類があります。
それぞれメリットとデメリットが異なり、現在の収入・貯蓄状況や将来のライフプランに応じて、どの制度を使うかが重要です。
例えば、財形貯蓄は株式や投資信託を運用する他の金融商品と比較して将来のリターンの期待値は小さくなりますが、低リスクで運用できるため、無理なく資産を積み立てたい人に向いています。
一方、老後に向けてより効率的に資産形成を進めるなら、株式や投資信託といった金融商品に投資・運用できて税制優遇も受けられる企業型確定拠出年金がおすすめです。
とはいえ、「どの制度をどのくらい利用すればいいのか?」は人それぞれです。自分に合った資産運用の方法を見極めるには、ファイナルプランナー(FP)に相談するのも一つの方法です。FPはライフプランや資産状況をヒアリングし、「まず何から始めるべきか?」を一緒に整理してくれます。
せっかくある制度を活用しながら、将来の安心に繋げていきましょう。
何でもマネプロに相談しよう
あなた専用のライフプランを作成し、家計・保険・資産運用・住宅ローン・不動産などお金の不安をまとめて解決する無料FP相談サービスです。
- ID:BM–683