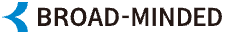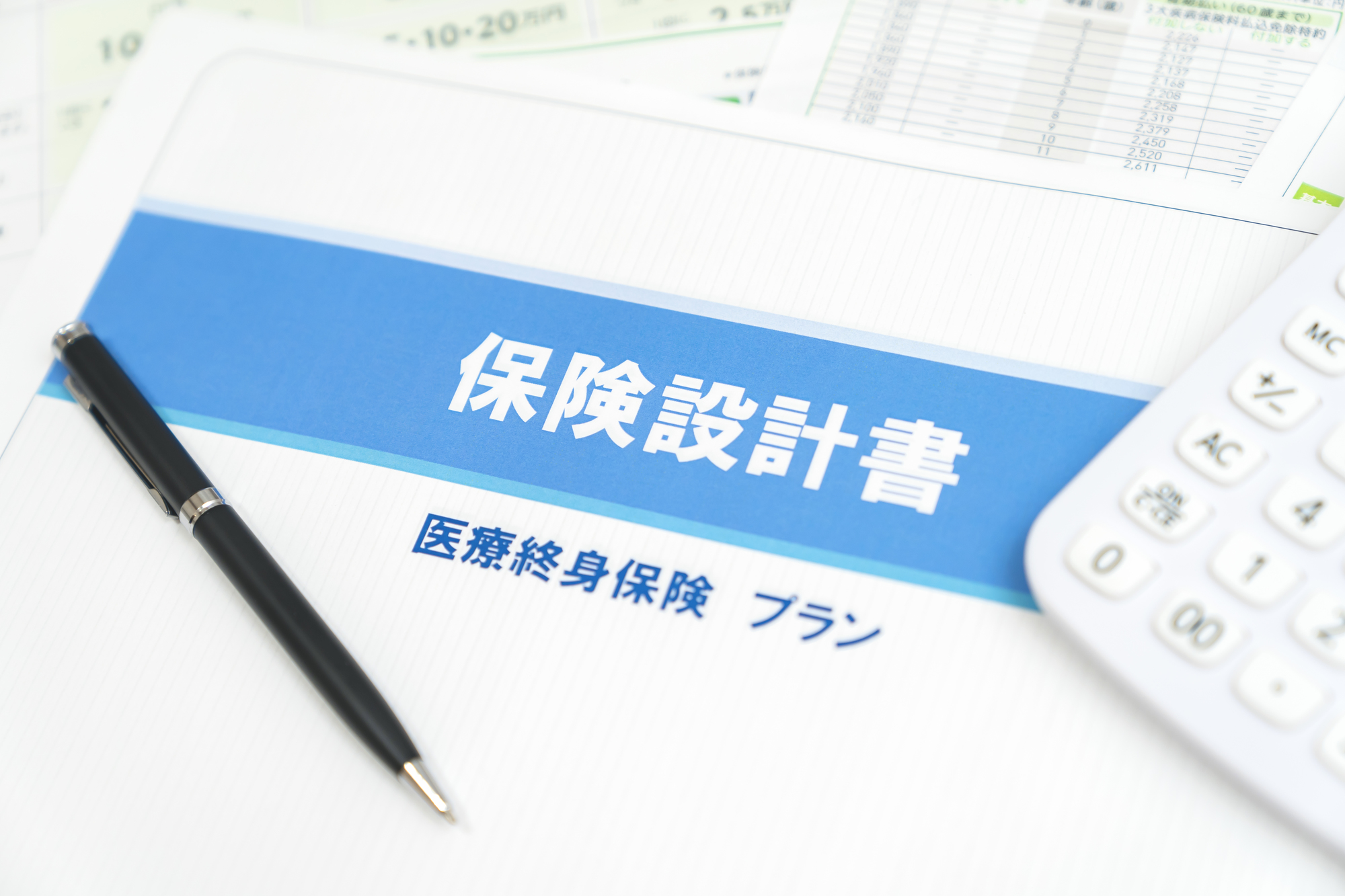掛け捨て型保険は本当にもったいない?貯蓄型との違いをFPが解説
 生命保険
生命保険
「掛け捨て型保険ってお金が戻らないんでしょう?なんだか損な気がする…」
そんなふうに感じたことはありませんか?掛け捨て型保険は、保険料が戻らない分、「払ったお金が無駄になるのでは」と不安に思われがちです。でも実は、掛け捨て型保険には効率的にリスクに備えられるという大きなメリットがあります。一方、貯蓄型保険は保障と同時に将来の資金を確保したい方に人気です。
このコラムでは、掛け捨て型保険と貯蓄型保険の違い、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、自分に合った保険を選ぶためのポイントをわかりやすく解説します。
あなた専用のライフプランを作成し、家計・保険・資産運用・住宅ローン・不動産などお金の不安をまとめて解決する無料FP相談サービスです。
何でもマネプロに相談しよう
目次
1. はじめに:「掛け捨て=もったいない?」と思う理由
掛け捨て型保険に対して「なんだか損な気がする…」と感じるのは、多くの人が保険に対して「支払ったお金が後で返ってくるもの」というイメージを持っているからかもしれません。実際、貯蓄型保険や終身保険のように解約時や満期時に返戻金があるタイプと比べると、掛け捨て型保険が「お金が戻らない」という点で損に見えるのは自然な感覚です。
さらに、次のような理由が「掛け捨てはもったいない」と思わせる要因になりがちです。
目に見える「リターン」がない
掛け捨て型保険は、支払った保険料が満期や解約時に一切戻ってこない仕組みです。そのため、「何も得られなかった」と感じやすい傾向があります。一方、貯蓄型保険は解約返戻金や満期保険金があるため、将来的なリターンをイメージしやすいのです。
「損得」で考えがち
私たちは日常的な支出を「コスパ」や「費用対効果」で考える傾向があります。そのため、掛け捨て型保険も「払った分が無駄になったのではないか」と捉えがちです。特に、保険を使わないまま契約期間が終了すると、「結果的に損した」と感じることがあるでしょう。
貯蓄意識とのギャップ
保険を「お金を貯める手段」として考える人も多いです。例えば、老後資金や子どもの学費を積み立てる目的で保険を選ぶ場合、掛け捨て型保険ではその目的を果たせないため、「もったいない」と思われがちです。
保険の本来の目的が見えにくい
掛け捨て型保険は、「万が一のときに備える」ための保障商品です。しかし、貯蓄型保険と比べると「お金が戻る安心感」がないため、そもそもの保険の意義を見失うこともあります。
掛け捨て型保険が合理的な選択肢となる理由
一方で、「もったいない」と感じる掛け捨て型保険には、貯蓄型保険では得られないメリットもあります。それは、保険料を抑えながら必要な期間に大きな保障を得られる点です。次章では、掛け捨て型保険と貯蓄型保険の違いについて詳しく解説し、それぞれのメリット・デメリットを整理していきます。
2. 掛け捨て型保険と貯蓄型保険の違いとは?
生命保険は大きく分けて、「掛け捨て型」と「貯蓄型」の2種類があります。
以下に、両者の特徴を簡単に比較しました。
【掛け捨て保険と貯蓄型保険の比較表】
| 特徴 | 掛け捨て型保険 | 貯蓄型保険 |
| 保険料 | 安い | 高い |
| 保障の大きさ | 大きい | 比較的小さい |
| お金が戻るか | 戻らない | 満期・解約時に戻る |
| 契約期間 | 一定期間 | 長期間 |
| 向いている人 | 短期間で大きな保障が必要な人 | 保障を持ちながら資産形成したい人 |
詳しくは、以下で解説します。
掛け捨て型保険とは?
掛け捨て型保険は、一定期間だけ保障を持つことができ、契約が終了すると保障も終了するタイプの保険です。特徴的なのは、保険料が比較的安く、万が一の際に大きな保障を得られる点です。ただし、保険期間中に保障を使わなかった場合、保険料は戻らず終了する仕組みです。
たとえば、定期死亡保険では、契約期間中に被保険者が亡くなった場合には保険金が支払われますが、期間中に何もなければ満期時の返金はありません。同様に、医療保険(定期型)やがん保険(定期型)も、一定期間の保障が終わると「更新」または「終了」となります。ただし、満期時に条件を満たせば保障を延長できる「更新」という仕組みがあるタイプの商品もあります。
主な掛け捨て型保険の種類
- ・定期死亡保険(一定期間のみ死亡時に保険金が支払われる)
- ・収入保障保険(死亡時に毎月一定額の給付金を受け取れる)
- ・医療保険(定期型)(病気やケガで入院・手術した際に給付金を受け取れる)
- ・がん保険(定期型)(がんと診断された際や治療の際に給付金を受け取れる)
掛け捨て型保険は、「一定期間だけ手厚い保障を持ちたい」というニーズに合っており、特に子どもが成人するまで、住宅ローン返済中など一時的にリスクが大きい時期に適しています。
貯蓄型保険とは?
貯蓄型保険は、保障を受けながら保険料の一部が積み立てられていく仕組みで、契約を継続することで将来的にお金を受け取れる可能性があるのが特徴です。「保障」と「資産形成」を同時に進めたい人に向いています。
たとえば、終身保険は一生涯の死亡保障を持ちつつ、途中で解約すれば解約返戻金を受け取ることができます。また、学資保険では子どもの進学時期に合わせて教育資金を計画的に積み立てられます。
主な貯蓄型保険の種類
- ・終身保険(一生涯の死亡保障があり、解約すると返戻金がある)
- ・養老保険(満期時に死亡保障と同額の満期金を受け取れる)
- ・学資保険(子どもの教育資金を積み立てる)
- ・個人年金保険(老後資金を積み立てる)
貯蓄型保険は、「保険料を払うなら、将来の資産としても役立てたい」という考えに合った保険です。ただし、早期に解約すると元本割れのリスクがあるため、長期間支払いを続けられるかが重要なポイントになります。
このように、掛け捨て型保険と貯蓄型保険では、保険料の性質や使い道、向いているライフステージが異なります。
3. 掛け捨て型保険のメリット・デメリット
ここでは、掛け捨て型保険の特徴を、メリットとデメリットに分けて見ていきましょう。
メリット① 少ない保険料で大きな保障を確保できる
掛け捨て型保険の最大の特徴は、同じ保障内容でも保険料を大幅に抑えられる点です。たとえば、月5,000円~1万円ほどの保険料で、数千万円の死亡保障を確保できることもあります。家計の負担を抑えつつ、必要な保障をしっかり準備したい方にとって、非常に合理的な選択肢です。
メリット② 必要な期間だけ保障を持てる
掛け捨て型保険は、10年、20年など契約期間を自由に設定できる「定期型」が主流です。たとえば「子どもが成人するまで」や「住宅ローンを完済するまで」など、ライフイベントに合わせて保障を持つことで、無駄のない保険設計が可能です。
メリット③ 浮いた保険料を別の目的に活用できる
掛け捨て型保険を選ぶことで、保険料を抑えた分をNISAやiDeCoなどの資産運用に回すといった、より自由度の高いお金の使い方が可能になります。保障は保障、資産形成は資産形成と分けて考えることで、それぞれの目的に合った形で効率的に将来に備えられるのが魅力です。
このように、掛け捨て型保険は、「一定期間のリスクに備える」ことに特化した、シンプルでコストパフォーマンスの高い保険です。
デメリット① 保険料が戻らない
掛け捨て型保険は、「保障を受けるためのコスト」として割り切る必要があります。契約期間を満了した場合や途中解約した場合、支払った保険料は基本的に返金されません。保障期間中に何も起こらなければ、支払った保険料はそのまま保障のための費用として消える形になります。
デメリット② 保障期間が限られており、更新時に保険料が上がる
多くの掛け捨て型保険は一定期間の契約であり、期間が終了すると保障は終了します。保障を継続したい場合は「更新」が必要となりますが、その際は年齢に応じて保険料が上がるのが一般的です。若いうちは安く加入できても、年齢を重ねるにつれて保険料の負担が増していく点には注意が必要です。
デメリット③ 老後の保障には向かないことがある
掛け捨て型保険は、基本的に一定期間のみの保障を提供するため、生涯にわたる保障を確保する目的には適していません。老後の医療費や葬儀費用など、長期的なニーズに備えたい場合は、終身保険など他の商品と組み合わせて考える必要があります。
このように掛け捨て型保険は、必要なときに必要な保障を効率的に用意できる反面、保障が期間限定であり、資産形成にはつながらないという特徴があります。長期的な備えが必要かどうか、自分のライフプランに合わせて上手に使い分けることが大切です。
4. 貯蓄型保険のメリット・デメリット
ここでは、貯蓄型保険の特徴を、メリット・デメリットの両面から見ていきます。
メリット① 計画的にお金を貯められる
保障を受けながら、定期的に保険料を支払うことで自然と貯蓄が進むのが大きな魅力です。たとえば学資保険では、子どもの教育資金を必要なタイミングで受け取ることができ、終身保険では老後資金として活用できるケースもあります。目的を持って積み立てをしたい方にとって、安心感のある手段となるでしょう。
メリット② 契約継続により資金を受け取れる仕組みがある
契約を一定期間継続することで、解約返戻金や満期金を受け取れる設計になっている商品が多くあります。たとえば、養老保険では満期時に死亡保障と同額の金額を受け取れることが特徴で、終身保険では年数に応じて解約返戻金が増加していく仕組みです。単なる「支出」とは異なり、将来の資金として活用できる可能性があります。
メリット③ 一生涯の保障を確保できる(終身保険の場合)
終身保険であれば、保険料の支払いが終わったあとも死亡保障は一生涯続きます。たとえ高齢になっても保障が途切れることはなく、「もしものときに家族に経済的な安心を残したい」という想いをかたちにすることができます。相続対策や葬儀費用の準備としても利用されています。
このように、貯蓄型保険は、保障と積み立てを同時に行いたい方や、教育資金・老後資金など将来の目的が明確な方にとって、計画的な準備を支える心強い選択肢です。
デメリット① 保険料が高く、家計の負担になりやすい
掛け捨て型保険と比べて毎月の保険料が高くなりがちです。たとえば、同じ保障額でも掛け捨て型なら月5,000円前後で済むところが、貯蓄型では月2万円以上かかるケースもあります。この保険料を長期間にわたり継続して支払う必要があるため、加入前に無理のない設計を確認することが大切です。
デメリット② 途中解約すると元本割れのリスクがある
保険は長く継続して初めて貯蓄効果が見込める商品です。契約から間もない時期に解約すると、返戻金が支払った保険料を下回る「元本割れ」が起きることも一般的です。急な資金需要が発生した際に備えて、保険以外の流動性ある資産とのバランスを考えることが重要です。
デメリット③ 利回りが低く、インフレへの耐性が弱い
貯蓄型保険は元本保証型の運用が中心となるため、一般的に利回りは控えめです。インフレが進んだ場合、将来受け取る金額の「実質的な価値」が目減りしてしまう可能性があります。そのため、保険だけで資産形成を完結させず、NISAなどと併用することでリスク分散を図ることが望まれます。
このように、貯蓄型保険は、長く契約を続けることではじめて真価を発揮する商品です。保険料の負担感や途中解約のリスク、運用面での限界を理解したうえで、ライフプランに合った活用を心がけましょう。
5. 掛け捨て型保険と貯蓄型保険、どちらが向いている?
ここでは、掛け捨て型保険と貯蓄型保険の特徴を踏まえ、それぞれがどのような人に適しているのかを整理しながら、選び方のポイントを見ていきます。
掛け捨て型保険が向いている人
掛け捨て型保険は、一定期間のリスクに備える保険として、シンプルで使い勝手の良い設計が魅力です。そのため、「必要な期間だけ大きな保障を確保したい」「保険料の負担をできるだけ抑えたい」という方に適しています。短期的に保障が必要なタイミングを狙って加入することで、効率よく万が一に備えることができます。
こんな人におすすめ:
- ・保険料を抑えながら大きな保障を得たい
- ・ライフステージに応じて保障内容を調整したい
- ・浮いたお金を貯蓄や投資に回したい
- ・一定期間だけ保障があれば十分(例:子育て中・住宅ローン返済中)
掛け捨て型保険は、特に子育て世代や住宅ローンのある家庭にとって、家計の負担を抑えつつ必要な保障を確保できる、実用的な選択肢といえます。
貯蓄型保険が向いている人
貯蓄型保険は、「保障を持ちつつ、将来のためにお金も貯めておきたい」「計画的に資金を積み立てたい」という方に向いています。長期的な視点で家計を管理したい人や、貯金が苦手だけれど強制的な積立の仕組みが欲しい人にとって、安心して続けやすい保険です。
こんな人におすすめ:
- ・長期間にわたり無理なく保険料を支払える
- ・保障を持ちながら資産形成をしたい
- ・投資に自信がなく、着実にお金を貯めたい
- ・教育資金や老後資金など、目的を持って積み立てたい
なお、貯蓄型保険は契約途中で解約すると元本割れの可能性があるため、ある程度の資金計画や継続意志が必要です。保障と貯蓄の両方を重視したい方におすすめです。
掛け捨て型保険と貯蓄型保険のどちらが適しているかは、「保障を重視するか」「貯蓄を重視するか」といった価値観や、ライフステージ、家計の状況によって異なります。
次章の「保険を選ぶときに大切なポイント」を押さえて検討しましょう。
6. 保険を選ぶときに大切なポイント
保険を選ぶ際は、掛け捨て型か貯蓄型かという違いだけでなく、自分自身のライフプランや家計とのバランスをしっかりと見極めることが重要です。ここでは、保険を選ぶうえで特に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
ポイント① 保険の目的を明確にする
まず、「自分は何のために保険に入りたいのか」をはっきりさせることが、保険選びの出発点になります。目的が明確であれば、必要な保障の種類や期間、保険のタイプも自然と見えてきます。
たとえば:
- ・家族の生活費や住宅ローン返済のため → 死亡保障のある定期保険
- ・医療費への備え → 入院・手術に対応した医療保険
- ・教育資金や老後資金の準備 → 貯蓄型の学資保険や終身保険
「誰のために・いつ・いくら必要か」を考えることで、自分に本当に必要な保障が絞り込めます。
ポイント② 家計に無理のない保険料を設定する
毎月の保険料は、無理なく継続できる範囲に収めることが大切です。
一般的には「手取り収入の5〜10%程度」が一つの目安とされていますが、これはあくまで参考程度の基準にすぎません。特に貯蓄型保険を選ぶ場合は、10%を超えるケースも多く、一律に判断することはできません。
大切なのは、教育費や住宅ローンなど他の固定支出も含めた家計全体とのバランスを見ることです。保障をしっかり確保しながらも、生活や貯蓄に支障をきたさない保険料に収めるよう意識しましょう。
また、掛け捨て型保険で保険料を抑え、浮いた分をNISAやiDeCoなどの運用に回すという方法も、特に若い世代には合理的な選択肢となる場合があります。
ポイント③ 継続と見直しの視点を持つ
保険は一度加入したら終わりではなく、ライフステージに応じた見直しが必要な商品です。
たとえば、結婚・出産・住宅購入・子どもの独立といったタイミングでは、保障内容の再確認や見直しを行うのがおすすめです。
また、特に貯蓄型保険の場合は、長期間契約を続けてこそメリットを得られる仕組みになっています。加入時には、
- ・最後まで無理なく支払いを続けられそうか
- ・途中解約した場合にどの程度返戻金があるのか
といった点もしっかり確認しておくと、後悔のない選択につながります。
保険は、「もしも」のときの安心を支える大切な手段です。自分の目的・家計・将来の変化を見据えたうえで、納得のいく選び方をすることが、長く安心して暮らすための第一歩になります。
まとめ:保険選びは専門家と一緒に進めるのが安心
保険は、万が一に備えるための大切な仕組みですが、「掛け捨てと貯蓄型、どちらが自分に合っているのか?」「保険料はどこまで出せるのか?」など、実際に選ぼうとすると迷ってしまうことも多いものです。
ライフプランや家計状況は人それぞれ。
たとえば:
- ・子育てや住宅ローンの時期に、大きな保障を効率よく持ちたい
- ・教育資金や老後の備えも視野に入れながら、資産形成もしたい
- ・保険料が家計の負担にならないか不安がある
こうした判断には、プロの視点があると安心です。
保険選びに迷ったら、専門家に相談するのも一つの方法
「どの保険が自分に合っているのか」「家計に負担をかけずに保障を確保するには?」といった疑問や不安を感じたら、一人で悩まずに専門家に相談するのも賢い選択です。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、あなたのライフプランや家計の状況をもとに、保険プランを一緒に考えてくれる頼れる存在です。また、保険の仕組みやそれぞれの特徴についても丁寧に教えてくれるので、初めて保険を検討する方でも安心です。
保険選びは、人生設計の大切な一歩です。迷ったときには、専門家の知識を活用しながら、自分に合った最適なプランを見つけてみるのも良いでしょう。
あなた専用のライフプランを作成し、家計・保険・資産運用・住宅ローン・不動産などお金の不安をまとめて解決する無料FP相談サービスです。
何でもマネプロに相談しよう
- ID:BM–707